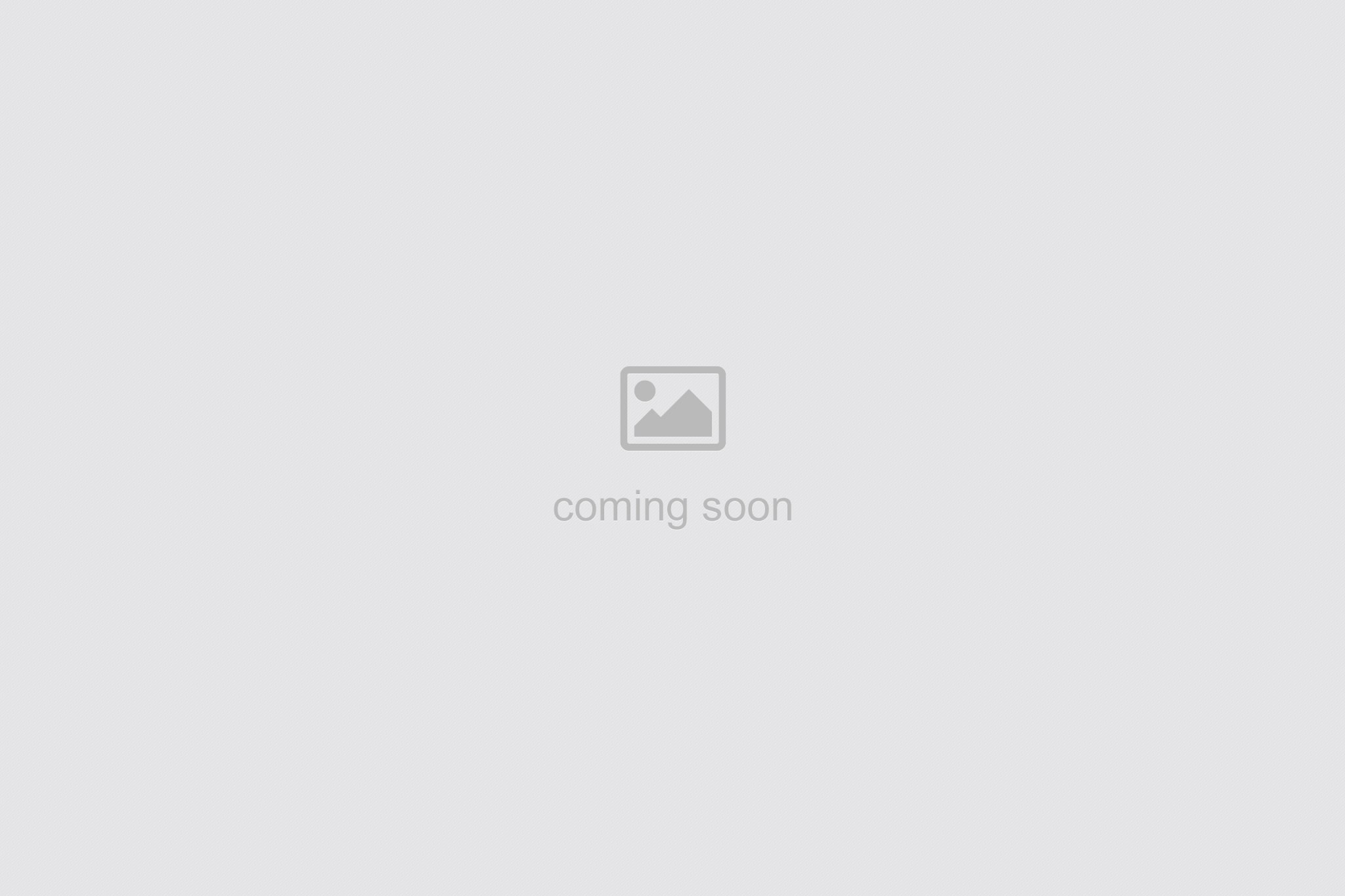富坂キリスト教センター
沿 革
●富坂キリスト教センターの歴史は明治時代にさかのぼります。そのころ、ドイツ人とスイス人によって東亜伝道会(Ostasien Mission 通称 OAM)が結成され、日本宣教の出発点のひとつに選んだのが富坂でした。富坂には教会、幼稚園、学生寮、戦後は富坂セミナーハウス等を運営し、多くの日本人キリスト者の様々な思い出を残す土地になりました。
●その後、1970年代に入って、ドイツ教会の海外宣教の方針が、ドイツの教会が主導する活動から、その国の教会とパートナーシップを組んで宣教活動を行う、という方針に変わりました。そこで誕生したのが富坂キリスト教センターでした。いくつかの既存の施設が整理され、1982年から富坂キリスト教センターの活動が始まりました。
●その後、1970年代に入って、ドイツ教会の海外宣教の方針が、ドイツの教会が主導する活動から、その国の教会とパートナーシップを組んで宣教活動を行う、という方針に変わりました。そこで誕生したのが富坂キリスト教センターでした。いくつかの既存の施設が整理され、1982年から富坂キリスト教センターの活動が始まりました。
◇お問い合わせ先◇
富坂キリスト教センター
TEL:03-3812-3852 FAX:03-3817-7255
okada@ceam.asia(岡田)
富坂キリスト教センター
TEL:03-3812-3852 FAX:03-3817-7255
okada@ceam.asia(岡田)
活 動
●富坂キリスト教センターは日本キリスト教団の関係団体、日本キリスト教協議会(NCC)準加盟団体です。研究活動は10名前後で構成される各研究会が数年間の共同研究を重ね、これまでに約200名以上の研究者、専門家、牧師の方々に協力いただき、30冊を超える研究書・出版物を生み出してきました。
●日本の教会は戦前のように圧政に再び巻き込まれることのない骨太の教会になるように、未来に大きな夢を持った教会として、宣教努力を重ねています。富坂キリスト教センタ-もこの教会の宣教に仕える研究活動を積み重ねていきたいと願っています。ドイツのハイデルベルクにある福音主義学際学術研究所の活動を手本にしながら、韓国神学研究所など韓国のキリスト教諸研究機関と共同研究も積み重ねてきました。〔一例『日韓キリスト教関係史資料II』(1995年 新教出版社)〕。これからも国際的な研究ネットワークを広げ、研究者の人的交流を重ねていければと願っています。
●日本の教会は戦前のように圧政に再び巻き込まれることのない骨太の教会になるように、未来に大きな夢を持った教会として、宣教努力を重ねています。富坂キリスト教センタ-もこの教会の宣教に仕える研究活動を積み重ねていきたいと願っています。ドイツのハイデルベルクにある福音主義学際学術研究所の活動を手本にしながら、韓国神学研究所など韓国のキリスト教諸研究機関と共同研究も積み重ねてきました。〔一例『日韓キリスト教関係史資料II』(1995年 新教出版社)〕。これからも国際的な研究ネットワークを広げ、研究者の人的交流を重ねていければと願っています。